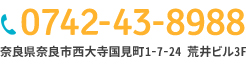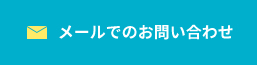灘高生の学習方法
思い浮かぶままに「学習の方法」を書き留めました。
(現在2児のパパ / 内科医 / 京都大学医学部卒 / 通称「タイタイのぱぱ」)
01 > 時間の使い方について
- 「2時間だらだらと」やるよりも「15分間集中」する。 ― 集中力が切れたら一休みしましょう。
- 5分・10分の隙間時間を大切にする。 ― 電車の待ち時間や乗車中の時間などのちょっとした時間を大切に。
- やりたいと思ったことをやりたい時にする。 ― あまり計画にしばられないこと。嫌な教科は放っといてお尻に火がつくまで待つもの。
- 興味がわいたらとことんやる! ― こうなったらシメタモノです。
02 > 理解するためには、手と口と頭を総動員する

(1)とくに語学に言えることですが「書きながら声を出す」ことは大切です。

(2)「暗記モノ」でも、何でも必ず「理由づけ」をする。
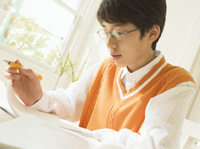
(3)初めの出会いで全力を尽くす。

(4)図・絵をかいて、他人にわかるように説明する。
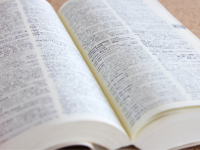
(5)辞書・参考書をひくのを億劫がらず、どちらも楽しく「読みましょう」。

(6)「返し縫い」は大切です。

(7)嫌いな勉強(?)もあきらめて、ちょっと好きになってみせる。 「興味を持って取り組もう!」
■ 暗記
= なぜそうなるのか「理由」をつけて「手」「口」「頭」を総動員させる。
■ 学習の定着
= なぜそうなるのか「図」「絵」を用いて、他人に説明できるようにする。
= 復習が大切。
■ 得意科目をつくろう
= 初めての出会いに全力を尽くそう。